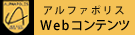資金繰りが破綻すると、会社は倒産します。
会社が倒産すると、経営者は責任を全て背負い、今までの生活さえも喪失するかもしれません。
そうなると、経営者夫婦の関係も微妙なものとなってしまいます。
その結果、経営状況が厳しくなって、離婚を選択される経営者は珍しくありません。

本来は、経営の厳しい状況でこそ、奥様の内助の功が求められるのでしょう。
経営者であるご主人のことを、もっとも理解し、最後まで頼りにできるのは奥様しかおられません。
だからこそ、経営者も奥様を頼りされるのだと思います。
ところが、経営が厳しくなり、その影響が家庭にまで及び始めると、奥様は現実の世界を見つめようとされます。
お子様の今後、そして奥様自身の生活をリアルに俯瞰することで、立ち位置に変化が起きても不思議ではないでしょう。
経営者の家族として、安定した生活が維持できなくなる悲しき現実に、ピリオドを打とうとされても仕方がありません。
経営者からすれば、奥様から三下り半を突き付けられたことになりますが、その様な離婚は珍しくもないのです。
しかし、他にも離婚の理由はあります。
奥様に迷惑を掛けたくないという、純粋な理由による離婚も存在します。
また、僅かに残る奥様の資産を確保するために、手段として離婚されることもあるでしょう。
万が一、事業が破綻した場合に備え、その後の生活を確保するための手段として、奥様の所有される資産を債権回収の対象から逃れさせようとされるのです。
離婚の理由としては、むしろ、これらの事例の方が多いのではないでしょうか。
今後の生活が不確定になる経営者として、そうしたい気持ちは判ります。
しかし、その離婚は現実的には意味がなく、お勧めできる方法だとはいえません。
経営者であるご主人が債務者だからといって、保証人でもない奥様にまで責任追及をされることはありません。
そもそも、夫婦であっても、明確に人格は別なのですから、保証人でもない奥様が債権回収の対象となることはなく、離婚される必要などないのです。
経営危機でこそ、ご夫婦は仲良くされるべきだと思います。
より良い結果を得るため、力を合わせて頑張ってください。
そして、今後の人生のために、夫婦としての資産を、夫人名義で構築されるべきではないでしょうか。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
↓
トップ経営研究所 ホームページ
会社再生・経営危機打開・事業承継オンラインセミナーをご覧ください,
↓
YouTubeチャンネル
ランキングです クリックして応援してください
↓
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
ランキングです クリックして応援してください
↓